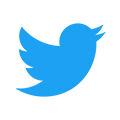コラム
責任実習でやってよかった遊び・失敗した遊び

保育の責任実習では、子どもたちと直接関わりながら、遊びや活動を自分で計画し、実践する貴重な経験を積むことができます。
計画通りにうまくいくこともあれば、想定外の出来事に戸惑ったり、準備不足を痛感したりすることもあるでしょう。
しかし、たとえうまくいかなかったとしても、その一つひとつの経験が大きな学びとなり、次への工夫や自信につながっていきます。
そこで今回は、責任実習で「やってよかった!」と感じた遊びと、「少し失敗してしまった…」という遊びを取り上げ、そこから得られた学びを紹介していきます。
責任実習でやってよかった遊び
・新聞紙遊び
新聞紙をびりびり破ったり丸めたりして遊ぶ活動は、年齢を問わず楽しめます。
子どもたちは想像以上に盛り上がり、破る音や感触を楽しんだり、丸めた新聞紙を投げ合ったりと、それぞれ自由な発想で遊びます。
準備も簡単で、片付けも一緒に楽しめるため、自然に子どもたちと協力しながら活動を終えることができます。
自由度の高い遊びは、子どもたちの発想力を引き出すのだと実感できるはずですよ。
・絵本の読み聞かせとごっこ遊び
絵本を読んだあとに、その内容に関連したごっこ遊びを取り入れると、活動への入りがスムーズです。
例えば動物が登場する絵本を読んだ後に「動物になりきろう!」と声をかけると、子どもたちはすぐにライオンやウサギになりきります。
本と遊びをつなげることで、子どもたちのイメージが広がり、物語の世界がぐっと身近に感じられるでしょう。
・製作遊び(紙皿のお面作り)
紙皿に絵を描いたり色を塗ったりして作る動物のお面は、工程が簡単で可愛らしい作品ができるため、成功しやすい活動です。
完成したお面をつけて遊びに発展させられると、さらに楽しさが増します。
子どもたちは「見て見て!」と誇らしげにお面を見せ合い、その後のおままごとや鬼ごっこにも自然に活用していました。
作品が遊びにつながることで、活動の満足感が高まります。
責任実習で失敗してしまった遊び
・ルールの複雑なゲーム遊び
椅子取りゲームをアレンジした遊びや、普段の集団遊びより少し難しい遊びは、ルールの説明に時間がかかり、子どもたちが飽きてしまうことがあります。
年齢に合ったシンプルなルールの大切さを痛感する実習生も多いです。
保育者の意図よりも、子どもたちが楽しく理解できることを優先する必要があると学ぶことができます。
・外遊びの準備不足
例えばシャボン玉遊びでは、予想以上にシャボン液がすぐになくなり、足りなくなることがあります。
「もっとやりたい!」という声に十分に応えられないと、子どもも保育者も思いっきり遊べず残念な気持ちになってしまいます。
準備物は多めに用意しておくことの大切さを学ぶことができます。
・静と動の切り替えが難しかった遊び
製作活動のあとにダンス遊びを取り入れるなど、静と動を組み合わせた活動では、子どもたちの気持ちや体の切り替えがうまくいかず、活動が収拾しにくくなることがあります。
例えば、紙皿でお面を作る製作の後に「さあ、みんなでダンス!」と声をかけると、子どもたちはまだ座ったままの気持ちや集中が抜けきっておらず、急に走り回ったりバラバラに動き出したりして、クラス全体の流れが乱れてしまうことがあります。
この経験から、活動を組み立てる際には、子どもたちが次の活動に自然に移れるように声かけや準備運動を工夫することの大切さを学ぶことができます。
まとめ
責任実習でやって良かった遊びと失敗した遊びをご紹介してきました。
責任実習での遊びは、成功も失敗も含めて貴重な学びの場といえます。
うまくいった活動には「子どもの発想を活かせる自由さ」や「準備物を工夫することで遊びが広がる楽しさ」があります。
一方、失敗した活動では「ルールの分かりやすさ」「十分な準備」「活動の流れを考える視点」が欠けていたことに気づけるのではないでしょうか。
反省点も含めて振り返ることで、自分にとっての保育のあり方が少しずつ形になっていくので、これからも「子どもたちが楽しみながら主体的に関われる遊び」を意識し、経験を積み重ねていけると良いですね。