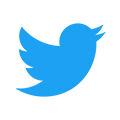コラム
施設実習ってどんなことをするの?施設別に紹介

施設実習は、子どもたちの多様な生活環境や発達段階を理解し、保育者としての実践力を養うための大切な学びの場です。
保育所実習と並行して行われることも多く、主に児童養護施設や乳児院、障害児施設、児童発達支援センターなど、さまざまな福祉施設で実施されます。
「保育所実習とは雰囲気が違うのかな?」「どんなことをするんだろう…」と不安に感じる学生も多いはず。
そこで今回は、施設実習でどのようなことを学び、どんな関わりを経験できるのかを、施設の種類ごとにわかりやすく紹介していきます。
どんなことをするの?
◎児童養護施設での実習
児童養護施設は、さまざまな事情により家庭での養育が困難な子どもたちが生活する場で、0歳から18歳までの幅広い年齢の子どもたちが暮らしています。
実習では、生活支援の補助、学習や遊びの支援、情緒的なかかわりなどが主な内容です。
子ども一人ひとりの背景を理解し、信頼関係の構築に努めることが求められます。
家庭的な雰囲気づくりや日々のケアを通じて、自己肯定感や社会性を育てる支援の大切さを学ぶ機会となるでしょう。
◎乳児院での実習
乳児院は、主に0~2歳の乳幼児が生活する施設で、家庭での養育が難しい子どもたちを保護・養育しています。
実習では、食事・排泄・睡眠などの基本的生活習慣の支援が中心です。
抱っこや授乳などの身体的接触を通じて愛着関係を築くことが重視され、細やかな観察力や応答的なかかわりが求められます。
保育士は単に“お世話”をする存在ではなく、乳児の心身の発達を支える大切な役割を担っていることを実感できる実習です。
◎障がい児入所施設、療育施設での実習
障がい児入所施設や療育施設では、身体的・知的な障がいのある子どもたちが暮らし、または通所しながら個々に合った支援を受けています。
実習では、子どもの特性を理解し、適切なコミュニケーション方法や支援技術を学ぶことが中心となります。
視覚支援、手話、絵カードなどを使った意思表示のサポートなど、多様な支援方法を体験できます。
子どもが安心して自己表現できる環境づくりや、自立に向けた支援のあり方を考える貴重な経験となるでしょう。
◎児童発達支援センターでの実習
児童発達支援センターは、発達に課題のある未就学児を対象とした通所型の療育施設です。
実習では、個別支援計画に基づいた発達支援プログラムを理解し、実践することが求められます。
保育士、作業療法士、言語聴覚士など多職種と連携しながら、チームで子どもを支える実践的な保育を学ぶことができます。
また、家庭との連携や保護者支援の重要性にも触れ、保育士としての幅広い役割を実感できる場でもあります。
◎母子生活支援施設での実習
母子生活支援施設は、生活困難やDVなどの事情を抱える母子が安心して暮らせるよう支援する施設です。
実習では、子どもへの保育的なかかわりだけでなく、母親に対する心理的・社会的支援の必要性についても学ぶことができます。
保護者との信頼関係の築き方や、母子の生活全体を支える福祉的な視点を身につける貴重な機会です。
◎児童心理治療施設での実習
情緒や行動に著しい課題を抱える子どもたちが入所・通所し、専門的な心理支援を受ける施設です。
実習では、子どもの心の状態を理解し、安心できる人間関係を築くことが求められます。
衝動的な行動への対応や、情緒の安定を目的とした遊び・創作活動への参加、カウンセリングの補助などを経験します。
「心に寄り添う保育とは何か」を考える機会になるでしょう。
◎自立援助ホームでの実習
自立援助ホームは、家庭を離れて暮らす15歳以上の青少年が、自立に向けて生活する施設です。
実習では、進学や就職の準備、生活スキルの支援、相談対応、社会的マナーの指導などに関わります。
保育という枠を超え、対人援助の実際や、自立支援の難しさ・やりがいについて深く考える経験となるでしょう。
まとめ
施設実習について、施設ごとにご紹介してきました。
実習では、子どもの生活や成長を支える現場に身を置くことで、「観察力」「対人関係力」「倫理観」など、保育士として大切な力を養うことができます。
また、家庭とは異なる環境で育つ子どもたちと関わることで、「子どもを全人的に理解する姿勢」や「多様な生育歴への配慮」といった専門職としての視点を持って支援することの重要性を学ぶ機会にもなるでしょう。
施設実習での経験を通して、子ども一人ひとりに寄り添う保育者としての在り方を見つめ直し、今後の保育実践に活かしていけるといいですね。